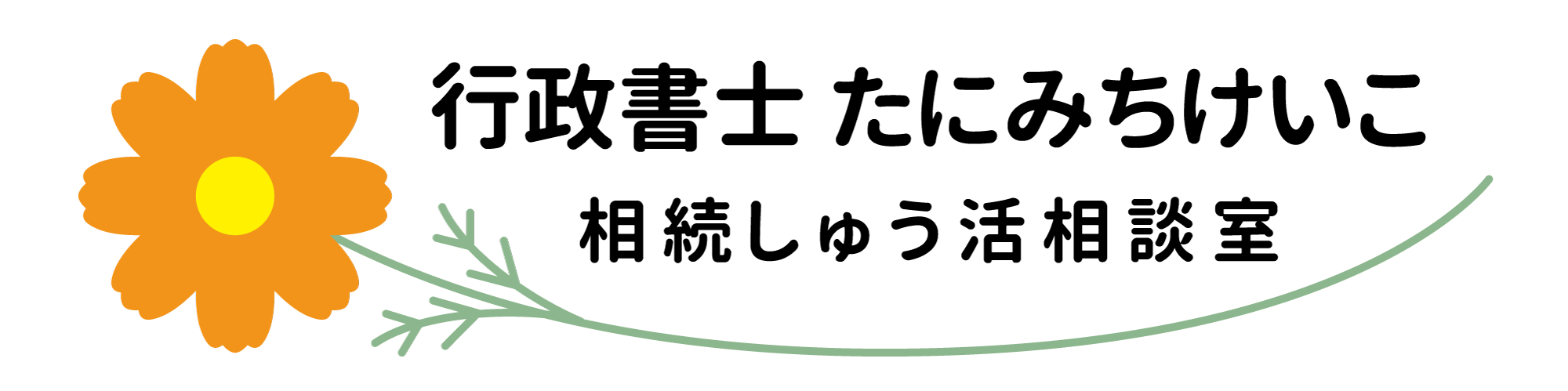「相続なんて、うちは関係ないですよ。財産なんてほとんどないですし。」
相談の現場で、こんなふうにおっしゃる方は少なくありません。でも実は、この「財産なんてないと思っていた」という思い込みが、後々思わぬトラブルを招くことがあるのです。

たとえば、実家の家と土地。
築年数が古くても、都市部や郊外の便利なエリアにあれば、それだけで数百万円から数千万円の評価がつくことがあります。預貯金があまりなくても、この「不動産」が相続財産の中心になることはよくあります。
70代女性の事例です。
ご主人が他界し、残されたのは築40年の一軒家と500万円ほどの預金。Aさんは「長男夫婦が一緒に住んでるし、話し合うまでもない」と思っていたそうです。
ところが、離れて暮らす次男さんが「自分にも当然に相続分がある」と主張してきました。結局、兄弟間で話がまとまらず、家庭裁判所の調停に進むことになりました。
Aさんのように「家などの財産は同居の子や長男が引き継ぐもの」と思っている方が多いのですが、実際には他の相続人にも法律上の権利があります。感情の行き違いや誤解が積もってしまうと、せっかく築いた家族の関係にヒビが入ってしまうこともあるのです。
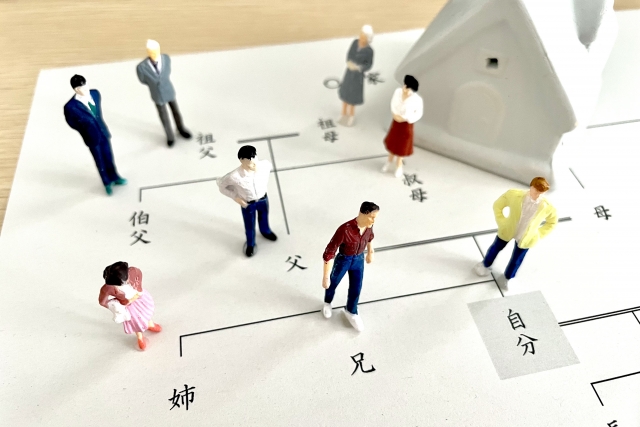
では、どうすればよいのでしょうか?
まずは、「うちにも相続の問題があるかもしれない」と気づくことが第一歩です。
財産が多い・少ないにかかわらず、相続はすべてのご家庭に起こりうること。だからこそ、元気なうちに家族で話し合ったり、専門家に相談したりすることが大切です。
「何かあってから考える」ではなく、「何もない今だからこそ備える」。
それが、家族を守る“思いやりの相続”につながります。